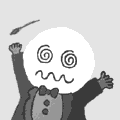今年のmeets.は朝が早い。
何回と触れているが、抱えてるステージの多い人がいるから練習に余念がない(アンサンブルステージ、楽しみにしていてください✨)。ステージの多くないなべちゃんは午前中から、単に自主練と称してワシワシと楽器をさわることにした。
練習とは、えらいもので、決して裏切らない。ハイポジや、指入れを丁寧にスピードを遅くから少しずつ通常にあげる、など、丁寧にさらうと、格段にひけるようになる。そんな話を、練習後のお茶で東京から通うマルチタスクのデキジョが吐露した。一夜漬け、とかではない、組み立てや、前後の流れや、関係性も把握しながらの丁寧な指入れ。
そこに「とーぜんですけどね。練習をすることも、練習が技術にこたえてくれるのも。」と、イケジョがささやいた。
とは言うもののさ。
わかってても、社会人、何やら他にも誘惑が多く、ついつい努力をおざなりにしがちで。
自主練の大切さって、わかりきってても、ついつい話題にしてしまうほど、効果は絶大で。ひっさしぶりに練習にきたセロの勇者は練習にこれなくても、動画見たりとか、指揮者の指示を丁寧に理解しながら個人練習に励むと、僕みたいにスキー漬けでも合奏にはいれるというか、わかってくるんだよね、曲が。とのたもうた。
そのとおり!!
その力こそ、メンバーの持つ底力と言える。
メンバーそれぞれが
やったことがある曲
やってみたいと望んでいた曲
それを脳内再生してるうちになんとなく曲の概要がわかってきていて、合奏で答え合わせみたいになり、わくわくが増す。既存の曲は、そうやって、みんなの底力もあって、楽しさや癒しに繋がる。
これが、今日の練習も、楽しかったね!の八割。
ただ、新曲は別!
イケジョが、ガストでひどくお疲れになりながらちょいもりポテトでドリンクバーを行き来していた。
「今日の練習。す、す、すっごくつかれた。」心中お察しします。でも一回ごとに、奏者に底力がついて、新曲が楽しくなってますよー。
ありがとう!
ありがとうだよーーー!!
本日は、自主練で繰り返し指入れをしたハイポジがスコンとはまり、心地よすぎて、お茶の時のお話しにひたすら頷く水飲み鳥なべちゃんてした!
水飲み鳥なんて知らないでしょー(笑)
ふっふっふつ